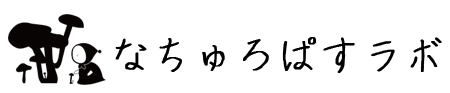小さなものから大きなものまで、日々の生活の中で避けられない「ストレス」。
現在のような特殊な社会状況において、さらに複雑になっているように思われます。

ストレスとは
「ストレス」とは、原因となる刺激「ストレッサー」によってカラダに起こる変化や生体恒常性(ホメオスタシス)にそれを基に戻そうとする反応のこと。
「ストレス」を引き起こす「ストレッサー」は大きくわけて3種類あります。
生体恒常性(ホメオスタシス)とは
生物が、体内の環境を一定に保とうとする性質のこと。
(気温の高い場合、汗をかいて体温を下げるなど。)
3種類のストレッサー
- 物理・科学的ストレッサー:寒冷、騒音など
- 心理的ストレッサー:不安や恐怖、不満、自身喪失など
- 生理的ストレッサー:体調不良や疲労、病気など
ストレスがカラダに及ぼす影響
生物にとって適度なストレスは必要であり、ストレスがないと逆に生命力が弱ってしまいます。
しかし、現代における過度なストレスは、心身の不調や病を引き起こしてしまいます。
過度なストレスによる体内の変化
step
1過度にストレスをかける状況(ストレッサー)が発生
step
2アドレナリンが分泌
- 心拍数が上がる。
step
3遊離脂肪酸値があがり、ドーパミン、ノルアドレナリン、エンドルフィンなどのホルモンが分泌
- 「遊離脂肪酸」:脂肪が分解されて血中に溶け出した脂肪酸で、体内の糖代謝や脂質代謝に関与している。
- 「ドーパミン」:やる気とモチベーションを高める。
- 「ノルアドレナリン」:集中力や判断力を向上。
- 「エンドルフィン」:「体内モルヒネ」と呼ばれ、鎮痛作用がある。
step
4各ホルモン、遊離脂肪酸の生成がピーク
step
5ストレス回避後、ホルモン・酸性値が減退
※場合によるが、体内システムが元に戻るには数日かかると言われている。
ストレッサーが無くなれば、Step5のように体内システムが元に戻る段階に入れますが、そうならない場合、Step4までがずっと繰り返されることになり、心身の不調や病を引き起こします。
最悪、死に至るストレスは「キラーストレス」と呼ばれ、ストレスの蓄積によって生じるといわれています。
大脳辺縁系によるストレスの感知と神経伝達物質の分泌
生体恒常性(ホメオスタシス)は、神経系・内分泌系・免疫系の3つのシステムの連携により働き、健康な状態を保っています。
外部からストレッサーの刺激を受けると、大脳辺縁系により感知されて、神経伝達物質が分泌されます。
神経伝達物質
- ノルアドレナリン:恐れ
- アドレナリン:怒り
- ドーパミン:嬉しさ・楽しさ
- セロトニン:落ち着き・癒し
- メラトニン:眠気
- アセチルコリン:リラックス
- エンドルフィン:恍惚感
これらの神経伝達物質は、自律神経や脳下垂体を刺激します。
刺激された自律神経は、各器官へとストレス刺激に応じた反応をするように働きかけ、脳下垂体は内分泌腺に働きかけてホルモンを血中に分泌します。
ストレスと自律神経
意思とは無関係に働く(心拍や血液循環など)自律神経神経は、「交換神経」と「副交感神経」に分けられ、バランスを取っています。
- 「交換神経」:エネルギーを作り出し、緊張や興奮という作用でストレスから身を守る。生体防御の最前線で働く機能。
- 「副交感神経」:鎮静、リラックス、休息の作用を司る。
この二種類の神経が、切り替わることでバランスを取ることで健康が維持されます。
しかし、ストレスを受け続けることなどが原因で、両者のバランスが崩れると心理的・身体的症状が現れるようになってしまいます。
ストレスと内分泌系
ストレスを受けたときに、特に重要とされる二つのホルモン、抗ストレスホルモンである「コルチゾール」と副腎髄質から分泌される「アドレナリン」があります。
- 「コルチゾール」:抗炎症作用、血圧上昇作用、肝臓のグリコーゲンを増加
- 「アドレナリン」:心拍数の増加、血管の収縮、血圧上昇、気管支拡張、瞳孔拡大、腸弛緩などの作用
これらの身体をストレスから守るために働くホルモンは、ストレスが過度であったり、恒常的に加えられたりする場合、ホルモンが分泌され続けるため、最終的に内分泌腺が機能しなくなることがあります。
これにより、身体の防御機能が落ちることで、様々な病気が引き起こされると考えられています。
自律神経や内分泌系のバランスが崩れた場合のカラダへの影響
- 内臓の不調
- うつ状態
- アレルギー(免疫バランスの崩れによる)
- 性格が攻撃的になる
など
ストレスの対策
1.ストレスとなっている問題への対処
問題を解決したり、ストレスとなっている原因から離れる。(可能であれば)
2.ストレスとなっている問題への認識を変える
「〇〇すべき」という固定観念があることにより抱えてしまうストレスを、自分の「〇〇すべき」と考えてしまうクセを認識することで対処する。
3.気晴らし(自分の機嫌をとる)
ストレスを受けたら、自分が心地よくなるような行動をとって、「快ストレス(善玉ストレス)」を自分に与える。
(問題解決が困難であったり、そこから離れることが不可能な場合は、これを積み重ねることが必要。)
4.瞑想
呼吸に意識を向けて瞑想。今、必要のない思考や、感じる必要のないストレスなどに心が侵されないようにする。
ストレスとなる問題が無くなるのが一番手っ取り早いですが、人間関係などにおいては難しいと言えます。
この中で、実践しやすいのは3.気晴らし(自分の機嫌をとる)ではないでしょうか。(瞑想が苦手でない人は4.瞑想も)
自分を心地よくする方法を、いくつか知っておけば、ストレス度合いによってその中から方法を選ぶこともできるようになります。
香り(好きな香りは「快ストレス(善玉ストレス)」は、瞬時に気分を変えることができ、
-

-
日本の自然を日常で感じる!和精油の世界
嗅覚へのアプローチにより、瞬時に気分を変えて自然の世界へと誘ってくれる精油。 最近では、日本の植物から精油ををつくられるメーカーさんも増えてきました。 私も和精油を使っていますが、その香 ...
続きを見る
運動することでコルチゾールが減少し、ストレスレベルを下げることが出来ます。
(コルチゾールの分泌→減少の正しいサイクルを取り戻し、ストレスに耐性ができてきます。)
-
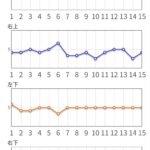
-
筋トレの継続と嗅覚反応分析の時系列変化
水はけのよい身体づくりのために、ゴールデンウィーク明けから筋トレ強化月間に入っております。 昨日までの嗅覚反応分析の4エリア(左上、右上、左下、右下)の時系列を確認してみました。 (最新 ...
続きを見る
嗅覚反応分析で、ストレス・疲労度、自分に合ったケア方法が分かります!
-

-
心身のバランスをグラフ化!「香りで自分を知る」嗅覚反応分析
”嗅覚で心と体を読み解く” ヒトの五感の中で最も先入観の影響を受けにくい”嗅覚”を使った体質分析法『嗅覚反応分析(IMチェック)』。 【特許名:生体情報生成方法(特許第5536272)】 ...
続きを見る